前編「90年代から現在までのアンビエント/ジャズなる音とその背景について」原雅明インタビュー①
特別企画|MUSIC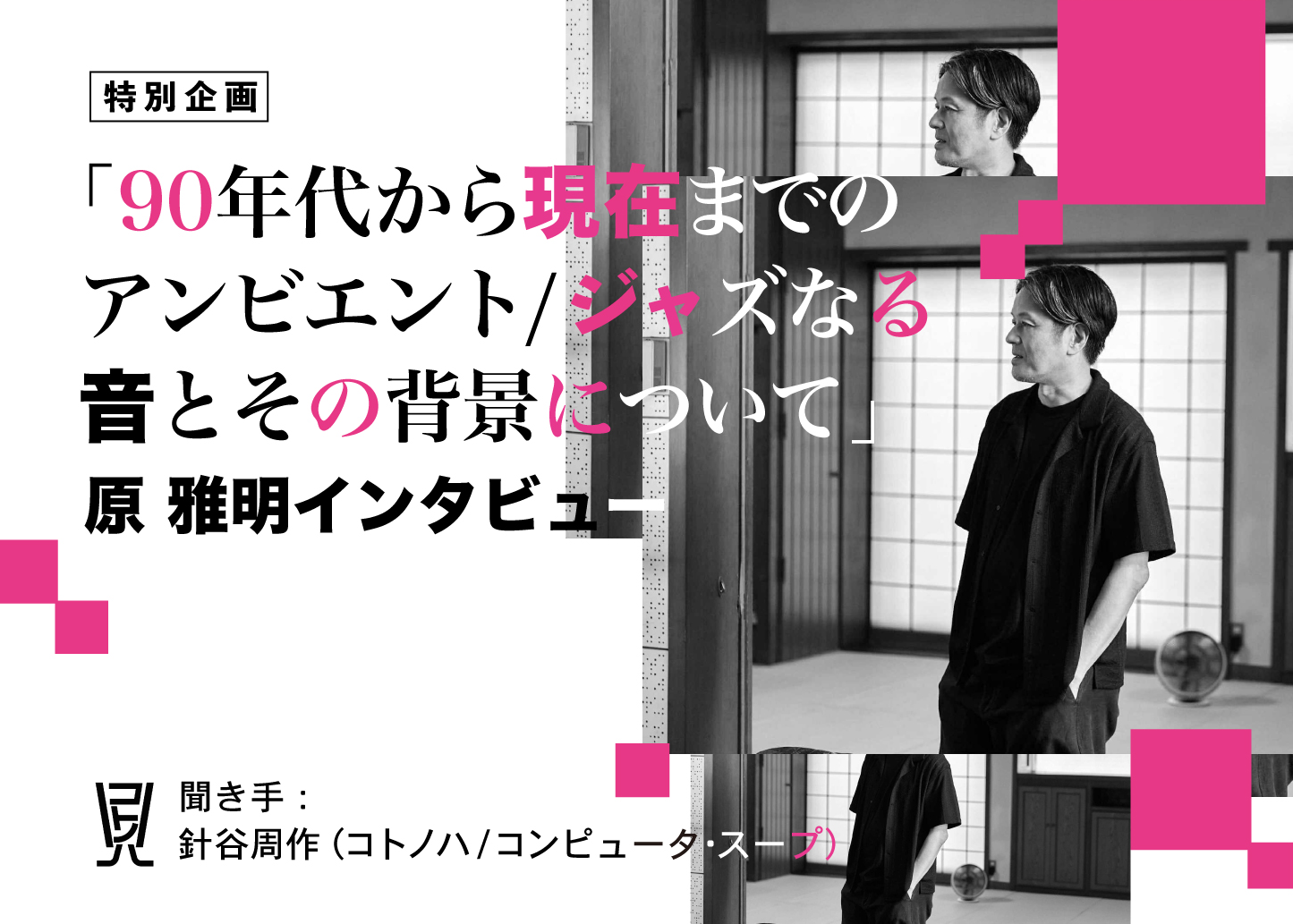
2025年11月半ば、マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノの音の接点に着目し、『アンビエント/ジャズ』(Pヴァイン)を上梓した原雅明さんから、これまで編集者/ライターとして、長年音楽や音楽家たちとともに仕事をしてきた氏の歩みについてお伺いする機会を得た。90年代半ば、佐々木敦さんとともにHEADZを立ち上げ、さらにレーベルsoup-disk、disques cordeを経て、現在はレーベルringsのプロデューサーとして、国内外のネットワークのなかで音楽を世に提案し続ける氏は、一貫して、ある空気感を求め、それらが漂う場に立ち合い続けている。
このインタビューは、私たちがコンピュータ・スープとして90年代から氏を介して関わってきた「音楽」的な場や時代について、理解の解像度を高めるのと同時に、いまもなお執筆やプロデュースで音楽に関わり続けている氏から、現在の音楽状況についても話していただいた。
聞き手:針谷周作(コトノハ/コンピュータ・スープ)

90年代のはじめから半ばのこと
針谷:いま、コンピュータ・スープのこれまでのことを振り返る「まだ『音楽』と呼ばれる前夜」というWEBでの連載をやってるんですけれども、私は90年代、たまたまモーリー・ロバートソンさんのラジオ番組『アクロス・ザ・ビュー』(J-WAVE)を聞いてレコードショップ「パリペキン」を知ったのがきっかけで、原さんや虹釜太郎さんと知り合うことになりました。
当時から私たちのCDをリリースしていただいたり、ライヴにお誘いいただいたり、お世話になってきたのですが、まずは原さんのこれまでの歩みをお伺いしたいなと思っています。
原:僕は大学を出てからふらふらしていて、たまたま拾われた事務所が、当時、宝島社の仕事をやっていた編プロで、いろいろ面白い人が出入りしてた。そこで編集のノウハウを教わって、それからいま思えば無謀なんだけど、いきなりフリーになって編集の仕事をあれこれやり始めたんだよね。そうした中で知り合ったのが、当時の『rockin’on』のデザインを創刊から手がけていたデザイナーの大類信(おおるい・まこと)さん。『rockin’on』の背の部分を並べると1枚の写真が完成するみたいな、ユーモアがあって、とてもセンスのいいデザインをやる人だった。大類さんは、自腹で『SALE2』(セール・セカンド)というザラ紙でボリュームがあって目を惹くデザインの雑誌を作っていて、それを手伝い始めるようになった。『SALE2』は、アーヴィング・クロウのようなフェティッシュ写真、ボンデージ写真を日本で最初にカルチャーとして紹介した雑誌だったんじゃないのかな。大類さんの事務所はマンションの一室にあったんだけど、輸入した写真集やボンデージ・グッズも販売していて、僕は、『SALE2』の編集をやりつつボンデージ・ショップの店員もやってた(笑)。それがまだ20代のころ。面白かったんだけど、ほかのこともやりたくて、ちょうど編集者を募集していた『シティロード』という雑誌の編集部に入った。
当時『シティロード』と『ぴあ』が、情報誌の2大勢力としてあった。映画、音楽から、美術や演劇などの上映、上演スケジュールが網羅されている雑誌なんだけど、ただ『ぴあ』と比べると、『シティロード』のほうがいろいろな人が書いたマニアックな記事が載っていて、読ませる雑誌でもあったんだよね。
音楽の担当が希望だったけど、求人してたのは映画の担当で、洋画と邦画、インディー映画などの単館上映の映画に分かれてて、僕は単館の担当になった。毎日のように試写に行って、映画のレビューを書いたり、情報を集めて上映スケジュールを並べるアルバイトの人たちをまとめたりしてた。『シティロード』では音楽の記事もたまに書いたりしてたけど、その時の音楽担当が仲俣暁生君だったんだ。
映画の上映をやっていた「アテネ・フランセ」も僕が担当していた関係で、先日亡くなってしまった安井豊さんとも知り合った。いや、安井さんはその前に樋口泰人さんの紹介で知り合っていたかも、ちょっと記憶があいまいだけど、安井さんはアテネ・フランセでゴダール特集をやったり、劇場ではかからないような映画の上映企画を立てたりしていた人で、優れた批評家でもあった。『シティロード』には映画を見て、星で点数つける「星取り評」っていうのがあって、多分、最初に「星取り評」をはじめたのは『シティロード』だったんじゃないかな。安井さんの書く文章が鋭くて面白いなと思っていたから、僕が推薦して「星取り評」の担当になってもらった。当時はFAXで原稿をもらってたんだけど、原稿を取りにアテネ・フランセに行ったりもしてて、そこで知り合ったのが、これまた亡くなってしまったけど青山真治君。蓮實重彦の下にいた立教大学の映画サークルの人たちもいた。安井さんは法政大学出身で、そこで音楽の企画もしてたから音楽の話もよくしたんだけど、でもこの話すると長くなっちゃうから割愛させて。

HEADZのこと
針谷:それで、映画関係ということで佐々木敦さんと知り合ったんですか?
原:佐々木君は別ルートで、彼が『DOLL』というパンク専門誌に書いているのを見て連絡したのがはじまりかな。当時、彼は「シネ・ヴィヴァン」という、六本木WAVEの地下にあった映画館の雇われ館長みたいな立場だった。佐々木君の下でバイトしていたのが、中原昌也君だった。それでシネ・ヴィヴァンではじめて会ったと思う。『シティロード』時代だから、80年代の末かな。
僕は92年くらいまで『シティロード』にいたんだけど、最後は経営がやばくなって、倒産してしまった。僕らは夜逃げ同然で一度解散したんだけど、九州の会社が買収をして再創刊した。でも、その会社が怪しそうだったんで、僕と仲俣君だけ行かなかった。というか、僕ら2人だけ態度が悪かったからパージされたんだけど。当時、『シティロード』を再建したいって手を挙げたところがもうひとつあって、それがアップリンク(UPLINK)だった。結局、九州の会社に買収されたから、アップリンクの浅井(隆)さんが、「じゃあ自分で雑誌やりたい」って言って手伝ったのが『骰子(ダイス)』という雑誌。
針谷:そうなんですね。『骰子(ダイス)』は当時、アンダーグランドなカルチャーを扱っていた貴重な雑誌でしたね。
原:当初から、僕は立ち上げだけやってやめるって言ってた。ほかにも編集をやってたから。『ミュージック・マガジン』とか、『remix』にも書いたり、音楽ライターも始めたころじゃないかな。編集の仕事のほうが、お金としては良かったから、軸足はあくまで編集者だったけど。ただフリーランスで、家でひとりで仕事をやってると煮詰まるなと思っていたら、同じことを佐々木君も思ってた。それで、どこか共同で仕事できる場所があるといいし、それで一緒にできることも生み出せるよねって話して、事務所(HEADZ)を作ったのが95年のことかな。
針谷:HEADZができたころに、私たちも呼んでいただいてお邪魔しましたね。あのころ、まだ山手マンションの地下に「渋谷ジァン・ジァン」がありましたね。
原:そうだったよね。事務所となる部屋を公園通りの山手マンションに見つけて、僕も佐々木君も車の免許を持ってなかったから、いまの僕の奥さんにレンタカーを運転してもらって佐々木君の知り合いの事務所からもらってきた机とかいすを運び入れたりしたよ。
針谷:しかし、よく山手マンションに空きがありましたね。
原:僕らの部屋の大家は「無印良品」で、事務所として使っていたのを貸しに出していたんじゃないかな。あのマンションにはほかにも音楽の事務所がいろいろ入ってて、まあ渋谷系の時代だよね。僕らは裏渋谷系のような存在だったけど(笑)。もっと詳しいことは、HEADZの歴史とか書いてるものがあるんじゃないのかな?
針谷:佐々木さんのインタビューなどでは読んだことはあるんですが、ほかにはないですよね。
原:多分、コムス(コンピュータ・スープ)と会ったのは、HEADZの立ち上げの頃だけど、もうその時クララ(「Kurara Autio Arts(クララ・オーディオ・アーツ)」)はあった?
針谷:あったかなあ……。
原:最初はなかったんだよね。立ち上げた時は僕と佐々木君の2人しかいなくてがらんとしてたけど、すぐに人が増えて、野界(典靖)君もクララを移転してシェアするようになった。野界君は本物の音の目利きで、見たことも聴いたこともないレコードを毎日のようにたくさん紹介してもらった。クララで買ったレコードはいまも手元に全部あるよ。残念ながら今年亡くなってしまったのだけど……。
針谷:私は1度か2度、クララへ立ち寄ったことがありましたが、それまでどこでも見たことのない音盤を扱っていたのに驚いた記憶があります。野界さんが亡くなってしまったのは残念です……。
原:山手マンションに入ったころに僕個人がやっていた仕事のひとつがレジデンツの翻訳本。湯浅学さんが監修で、湯浅さんの奥さんが翻訳をしてたんだけど、その装丁を祖父江(慎)さんにお願いしようと思って直談判しに行った。それで祖父江さんの事務所で受けてくれることになって、担当したのが当時そこで働いていた佐々木暁君だった。あがってきたデザインがあまりによかったから、この人は天才だと確信した。そのころから『FADER』みたいな自前の雑誌を作りたいって話はしてたと思うけど、それにはデザイナーも必要だし、通訳も必要だなと思ってた。それでデザイナーとして佐々木暁君をHEADZに招いた。暁君も独立を考えていたタイミングだったようで、暁君の部屋を用意して、常駐してもらった。HEADZではそのころトイズファクトリーの仕事をしてて、「NINJA TUNE」のものとかやってたんだけど、あるとき、DJヴァディムのインタビューの通訳として現れたのが、(バルーチャ・)ハシム君だった。いろいろな通訳の人を知ってたけど、すごく優秀だなと思って、これまたHEADZに誘った。それと当時『remix』の編集してた河野(有紀)さんにも来てもらって、彼女も『remix』を辞めるタイミングだったから。そうやって人が揃ってきて、『FADER』を作った。あの当時、まだ音楽のバブルは続いていて、レコード会社の仕事で冊子を結構作ったりもしてた。HEADZという体制にすると、「通訳もデザインも編集もできます」っていって、丸ごと受けられるようになったからね。
針谷:会社形態ではなかったんですか?
原:いま思うと、僕らは本当に素人のスタンスのまま、来日公演のような仕事までやっていた。いまだったらみんな会社にするよね。あの当時は会社をつくる資本金が高くて大変だったというのもあったけど。レコード会社からお金をもらって、『FADER』の表4に広告出してもらったんだけど、僕らがつくらないから、広告出した作品がリリースされても本ができてないっていうことも平気であった。『FADER』は評判はよかったし、デザイナーにもほかでできない冒険をしてもらって、みんながやりたいことだったから手応えも感じてたけど、作るのがとにかく大変だったな。
針谷:文字がとても小さくて、ぎっしりと内容が詰まっていましたね。佐々木暁さんのデザインもとても先鋭的で、当時、興奮しながらページをめくっていました。「ソフトウェア・オン・デマンド」の特集記事がいまも記憶に残っています。その頃、音楽制作の中で、Max/Mspや、SuperColliderなどを使ってプログラミングすることがブームになっていましたね。私も当時、一部で流行ったリアルタイム画像処理ソフト「nato」のプログラマーに会いにオランダの電子楽器スタジオ「Steim」まで行ったりしていました。原さんがHEADZにいたのは『FADER』4号までですか?
原:オウテカとDJケンセイの表紙のときまで。たしか4号。99年じゃないかな、僕がHEADZから抜けたのもそのころ。でも、その後もずっと僕はHEADZの人と思われていたようだけど(笑)。
針谷:「soup-disk」もやられてましたね。私たちも最初のコンピレーション・アルバムに入れてもらって。最初のコンピには、モンタージュさんが入ってましたね。
原:モンタージュの山道(晃)さんは、池田亮司と一緒にやってた人で、池田亮司と虹釜君はつながってた。最初のsoupのコンピ2枚は、そうやって虹釜君がつなげてくれた人脈が主だったと思う。『FADER』もやり始めたくらいだから、結構デモテープもらったりすることも多かったので、そこから後でリリースしたこともあったけどね。

レーベル「soup-disk」の周辺
針谷:私たちは、90年代の初めから半ばごろまで、渋谷の路上で即興演奏をしてましたが、soupの最初の方のコンピレーション・アルバム『Silverlization ー銀化ー』なんか、いい意味で「わい雑」な印象だったじゃないですか。混沌ともいえるあの雰囲気が、私たちもなんか好きでした。
原:soupは虹釜君と一緒に立ち上げて、彼は自分で不知火(しらぬい)もやっていて、リリースしたいものがものすごくたくさんあったけど、僕が全然追いつかないっていうのが実情だった。
soupの初期のころの、いま針谷君の言った混沌とした空気感みたいなのは好きな世界だったんだけど、日本のインディのレーベルってあの当時、僕らの周りにはスズキスキーを出してたTransonicのようなテクノ系や、エクスペリメンタル系のレーベルはあったんだけど、そこにはない世界だったと思う。僕も虹釜君もヒップホップの影響も受けてて、DJプレミアやDJクラッシュとか、初期のMo’WAXやNINJA TUNEもそうだったけど、ああいうアブストラクトな音使いはもちろんのこと、粗い、いまのサンプラーと全然違う、ビットレートの低いサンプラーから出る音そのもの、それをまとったビートそのものに惹かれてた。虹釜君に言われてAKAIのS01っていう、いちばん簡素なサンプラーを買って、ループも作ってた。そういう質感とかがとにかく好きで、それを身体に染み込ませるようにサンプラーをいじっていた記憶がある。
あとはジャズ。ジャズも、スマートでクリアな、コンテンポラリーのジャズじゃなくて、フリージャズはもちろんだけど、レコードを通してもう一回聴くようなジャズというか、サンプリングするときのネタものとしてのジャズの質感、空気感みたいなのは僕らが共通して好きなものだった。それを体現してたのが初期のsoupだと思う。
ただ、それって、全然受け入れてもらえなかった。だって、ヒップホップそのものじゃないし。ましてやジャズでもない。意外なところから「いいですよね」って言ってもらって、そういうのはとても嬉しくて、励みにもなったけどね。多分、虹釜君のほうがレーベルをやるのに、僕よりはるかに肝が座ってたと思う。彼はやりたいことが明確にあって、それでどんどんその世界を極めていったのが不知火や360° Recordsだった。一方、僕は迷いや疲れがあったように思う。好きな世界だけど、出せば出すほど赤字で、何のためにやってるかわかんなくなることは正直あったから。
時代が違っていれば、それを海外の人が発見してくれて広めてくれたりとかもあったかもしれないと、いまになっては思うけどね。結果的にもうちょっと経ってから、コンピュータ・スープとヤン・イェリネックがアルバムを出したり、カッパブラックをポールのレーベルscapeからリリースしてくれたりとかあったけど、それでもこちらの状況は変わらずで、自腹切ってリリースして、CDだけじゃなくて海外でプレスしたレコードも自宅に在庫抱えて、ウィ・ディストリビューションの山崎(泰浩)さんのところに納品するみたいなやり方をただ続けていたんだよね。
針谷:ウィ・ディストリビューションは横浜のほうにあったインディーズの音盤を扱う山崎さんひとりでやっている流通会社でしたね。私もよく山崎さんのところへ行って、いろいろな音楽を聴かせてもらいました。
原:山崎さんにはお世話になりっぱなしだったね。感謝の気持ちしかないよ。

コンピュータ・スープの90年代〜2000年
針谷:私たちもあの当時、原さんたちからアルバムを出してもらって、そんなに売れるジャンルの音楽ではないのに、「音楽で食っていこう」みたいな意気込みで日々過ごしていたところもありました。いろいろ頑張って営業したりとかしてたんですけど。
あのころ、いまでいう奧渋のほうに移転する前の渋谷のアップリンクでライヴをやったり(現在は渋谷店は閉館)、DJ SAKさんから誘われて、クラブエイジアでライヴをやったりしていました。
あれから私たちは、メンバー同士の行き違いが多くなって、活動が続かずに途切れてしまった感があるのですが。マーカス・ポップ(Oval)やヤン・イェリネックともコラボレーションするようになっていった時期でもあったんですけどね。
原:その前に、コムスが珍しくやる気出してたときがあったでしょ(笑)。リキッドルームでやったり、田中フミヤ主催のMASKというイベントでYELLOWに出たり。
いままでのアンダーグラウンドの小さい場所だけじゃなくて、もうちょっといろんな人が来る場所でもライヴしてほしいなっていうのはあって、僕が紹介したのもあると思うけど、向こうから関心を持ってくれたきっかけになったのが、多分soupから出した『Toisarasi』じゃないのかな。
1枚目(『Computer Soup』)の時はまだ知る人ぞ知るという感じだった。『Toisarasi』は、マーカスとかヤンに聴かせたのを覚えてて、それで反応があったのがきっかけとして大きかったと思うな。
針谷:それまでのアナログ楽器でのインプロ中心のアルバムとは違って、結構音がはっきりしているアルバムですよね。『Toisarasi』は。
原:それまでのコムスの、いい意味で茫漠とした音の感じは薄らいでいるかもしれないけど、パソコンでグリッドに沿って作ってる音ではない揺らぎはあったし、堀君のトランペットがちゃんと鳴っていて音の層になじんでもいたし、まさに「アンビエント/ジャズ」で、そういう音の走りでもあったと思うんだよね。
だから『Toisarasi』出したときは、暁君のデザインも含めて、ポップって言い方が正しいかどうか分からないけど、もうちょっと広いところで聴いてもらえる可能性を秘めてたと思うんだ。
それで、山辺(圭司)君(LOS APSON<ロスアプソン>店主)のところから、『DREAM MONS』もリリースしたよね。
針谷:ロスアプソンの山辺さんがze-kooというレーベルを立ち上げて、そこから出してくれたのが『DREAM MONS』というアルバムでした。これは『Toisarasi』の後にリリースされました。自由が丘のスタジオで録音して。CDに付属する冊子には、山辺さんが絵を描いて、岡本敏子さんや大竹伸朗さん、浅野忠信さんらには絵と曲にあわせた短いポエムのようなものを書いていただいて。山辺さんやラストラムの佐藤さんには大変お世話になりました。
原:山辺君のところは、半分メジャーだったよね。
針谷:そうですね。ze-kooは、Sony傘下だったラストラム内のレーベルでした。
原:だから、そうやって広がっていくきっかけになったのは、多分、『Toisarasi』だったんじゃないかなって。
針谷:ギターとベースをやっていたメンバーが、楽器をステップシーケンサーに変えたタイミングが『Toisarasi』だったんですよ。
原:そうだ、初期のコムスは一応、普通のバンドっぽい編成だったんだよね。その変化も興味深かったし、この音はいまこそ聴かれそうな気がするけど。
コムスのメンバーも含めて、サッカーをみんなで始めたのは、いつだったんだろう。田中フミヤ率いるFC Chaosともよく試合をやってて、いつも僕らは負けてたんだけど(笑)。Onsaの庄内(正行)君と「corde(コルド)」という事務所を始めて、disques cordeというレーベルをやる前だったから、2000年代のはじめかな。そのころにマーカスが来日してコムスとつながったんだよね。でも、どうしてつながったのかは思い出せない。『Toisarasi』のCDを送った覚えはあるんだけどね。とにかく、その来日でマーカスが自前のスパイクを持ってきて、僕らと一緒にサッカーをやったの。
針谷:あれ、そうでしたか?!
原:マーカスが、大久保君のバイクのうしろに乗って、あのころ、僕らが毎週のようにサッカーやってた多摩川の河川敷のグラウンドにやってきた!
針谷:それはびっくりです。私は当時、音楽にしか興味がなくサッカーへは2回くらいしか行ってなかったので(笑)。
原:意外にもマーカスがサッカーうまくて、びっくりしたよ。最初に鋭いセンタリングを上げて、みんながビビったのを覚えてる(笑)。
ヤン(・イェリネック)とのアルバム(『Improvisations And Edits Tokyo, 09/26/2001』)って『Toisarasi』のあとだよね。
針谷:そうですね、あとですね。
私も1999年に『Salon』というインディペンデントの雑誌を立ち上げて、その後VHSカセットでリリースした2号目の取材で、ベルリンにあったマーカスの自宅兼スタジオへ行ったりして。行く前にマーカスから「日本でこのゲーム買ってきて」って頼まれてゲームを買っていったりしてましたね。確か「太鼓の達人」なんかも買っていったような。
振り返ればあのころから、本を作って身近なところは自分で納品して、後日、現金で精算ということをいまに至るまでやっています(笑)。
原:『Salon』は、針谷君が最初に作った雑誌でしょ。
コムスが海外に紹介されたのって、Plug Researchがチェシー(Chessie)とのスプリットEP『Lost, Not Found』を作ったのがきっかけだったよね。『Toisarasi』から2曲が収録されていた。その後、ヤンとのアルバムが、海外でもリリースされた。そもそもはsoupで企画してリリースしたものだけど、それだと国内にしか届かないから、ヤンの紹介でベルギーのSub Rosaというレーベルからもリリースされた。
あれが出て、海外からは反応があってすごい喜んだけど、国内の反応は鈍くて、ちょっとがっかりしたね。それまでクリック・ハウスとして聴かれていたヤンがエクスペリメンタルな音楽性に移行し始めた時期で、それが受け入れられないという状況もあったとは思うけど。
針谷:『Improvisations And Edits Tokyo, 09/26/2001』が出た数年後に、ベルリンにあったヤンのスタジオ兼自宅まで行ったことがありました。玄関先まで訪ねていったら、「え、本当に来たのか?!」と驚かれて、なぜか家には入れてもらえず、トラムに乗ってちょっと離れたカフェへ行って話すことになりました。当時、私がディレクションをやっていた「SOUND X VISION」というプロジェクトで会いに行って。最近、コンピュータ・スープの音源をサブスクで配信するようになって、どこからストリーミングされたかがわかるんですが、ヨーロッパやロシアが多いんですよ。
原:特に日本の若い人は、たぶんコムスを知らないと思う。だから、このインタビューもきっかけに、ちゃんとプロモーションしよう(笑)。
針谷:ありがとうございます(笑)。
つづく(後編は12月25日に公開予定)
原雅明プロフィール
文筆家、選曲家、プロデューサー。各種媒体への寄稿やライナーノーツの執筆の傍ら、レーベルringsでレイ・ハラカミの再発などのリリースに携わり、ロサンゼルスのネットラジオ局dublabの日本ブランチの設立に関わる。リスニングや環境音楽に関連する企画、ホテルの選曲を手掛け、都市や街、自然と音楽とのマッチングにも関心を寄せる。早稲田大学非常勤講師。著書に『アンビエント/ジャズ――マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜』(Pヴァイン)、『Jazz Thing ジャズという何か』(DU BOOKS)など。








