後編「90年代から現在までのアンビエント/ジャズなる音とその背景について」原雅明インタビュー②
特別企画|MUSIC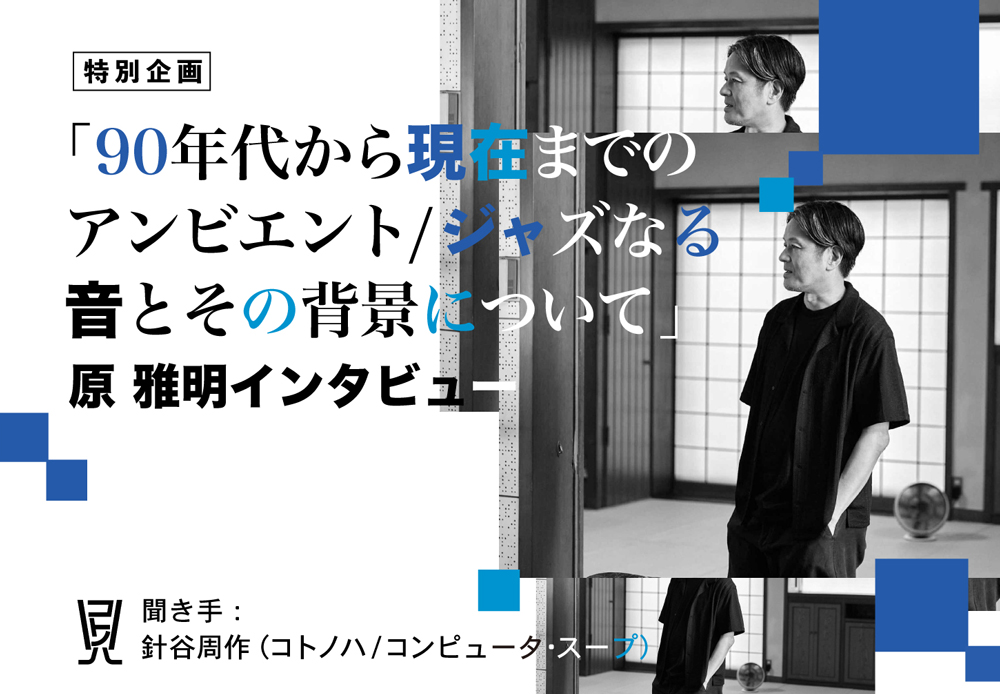
2025年11月半ば、マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノの音の接点に着目し、『アンビエント/ジャズ』を上梓した原雅明さんから、これまで編集者/ライターとして、長年音楽や音楽家たちとともに仕事をしてきた氏の歩みについてお伺いする機会を得た。90年代半ば、佐々木敦さんとともにHEADZを立ち上げ、さらにレーベルsoup-disk、disques cordeを経て、現在はレーベルringsのプロデューサーとして、国内外のネットワークのなかで音楽を世に提案し続ける氏は、一貫して、ある空気感を求め、それらが漂う場に立ち合い続けている。
このインタビューの目的の1つは、コンピュータ・スープとして私たちが90年代から氏を介して関わってきた「音楽」的な場や時代について、理解の解像度を高めことにある。いまもなお執筆やプロデュースで音楽にかかわり続けている氏から、現在の音楽状況についてもひもといていただいた。
90年代から現在までの「アンビエント/ジャズ」的な音とその背景について。後編です。
聞き手:針谷周作(コトノハ/コンピュータ・スープ)

音楽レーベルの持続可能性について
針谷:原さんは、soup-diskのあとにdisques cordeをやられて、現在ではringsをやっていますが、長く音楽レーベルを続けられてきて、どうやったらいま音楽を広めることができると感じていますか?
原:まず、少なくともsoupのころは音楽を広めたいからやっていた、とはいえない。ただ、やりたいからやっていたというほうが素直な答えかな。そのあと、変わってはきたけど、その問いに答えられるような何かを成し得たとは思ってないんだよね。アーティストに迷惑をかけたこともあったし。だから、個人的なスタンスのことしか話せないのだけど……。そのあともレーベルを続けられたのは、音楽について書くだけだと得られなかったことが得られたからだと思う。具体的な人間関係もそうだし、経験とか、知識とか、自分で体感したことも含めて。いわゆる音楽ライターとして、好きな音楽や仕事で振られた音楽についてあれこれ書くっていう仕事をしていただけだと見えなかった視点が、最終的に書くことにも向かわせたんじゃないかと。それは自分にはとても大きなことだった。ただ、その代わり、ライターとしてのバランス感覚に欠けるというか、より作り手に近い立場に立ってしまうこともあるんだけどね。
あと、レーベルをやり始めたときって、80年代のポストパンクとかニューウェイブとか、テクノやハウスもそうだけど、そういうインディペンデントなレーベルの延長にある感じのスタンスだった。身近にある面白いと思う音楽を出してるだけというか、あまり商売気がなくて、だけどなんか変な情熱というか、淡々と続けていく気力だけはあるみたいな。少なくとも僕はそこに使命感とかなかった。
いまは、そもそもレーベルの立ち位置が違ってきていると思う。インディペンデントといっても、アーティストのマネジメントまでしっかり見て、ある程度売れる人の基盤の上で成り立っているケースもあるよね。そういうのが成功例としてある一方で、アーティストが自分で出すこともできる。全部を抱え込まなくてもいいような仕組みもできていて、配信のシステムもちゃんとあるし、レコードやカセットテープでも出せる選択肢もあるから。でも、レーベルという第三者のフィルターを通してリリースされることで広がりを持てて、関心を寄せられるという価値そのものはなくならないと思うんだ。いまある形のレーベルではなくなったとしてもね。
いまやってるringsは、それまでと何が違うかっていうとディスクユニオンでやってるレーベルなの。だから要は自分のお金ではない。僕はディスクユニオンとプロデューサー契約をして、リリースの提案をして、企画が通って予算が付けば、プロデューサー印税みたいな形で、売れた分は支払われる。cordeまでは完全に自腹切ってて、それが続かなくなったのは2010年代に入ってからだった。そこに至ることで話し忘れていたけど、LAのネットラジオのdublabを立ち上げたフロスティ(マーク・マクニール)がsoupを含めた日本のインディの音楽に興味を持って、僕にコンタクトを取ってきたのが、1999年、ちょうどdublabがスタートする直前で、僕がHEADZを離れた頃だと思う。
)参考
短期連載「今また出会う、レイ・ハラカミの音楽」 第2回:マーク・“フロスティ”・マクニールが語る、「流動体のような音楽」との出会い・その特異性
そのとき以来、dublabとはつながりができて、コムスをリリースしたPlug Researchもdublabがつなげてくれたんだ。その後、ハシム君がLAに移住してdublabとのつながりはより強くなって、日本のブランチを作って配信を始めるようになった。また、LAではLow End Theoryというパーティがスタートして、ビートメイカーがインストのビートだけでライヴをする場が盛り上がりを見せた時期だった。それまで裏方だったビートメイカーにダディ・ケヴたちが焦点を当てて、価値観をひっくり返した。そこからフライング・ロータスも登場したんだよね。ちなみに彼のデビュー作『1983』もPlug Researchだった。ハシム君から話を聞いて、僕も実際にLAに行ってみて新しい流れを紹介したいと思ったんだ。それで日本でLow End Theoryもやったし、音源をリリースすることもやった。
参考)
これからの音楽業界は、小さな組織がイノヴェイションを起こす。「Low End Theory」創始者に訊く、アートファーストの哲学:starRo連載『Let’s Meet Halfway』
でも、一方で日本でもついにCDが売れなくなっていた時期だった。そのときはウルトラ・ヴァイヴがディストリビューターをやってたんだけど、製造費は相変わらず僕が出してた。ただ、プレス会社への支払いなどはウルトラ・ヴァイヴが間に入って、あとで売上から相殺してた。最初にまずはお金を払うという精神的な負担は軽減されたけど、そうして多少楽になったら、もうCDベースのリリースは自分がやらなくてもいいと思えてきて、そこで一旦辞めて、区切りをつける気持ちにもなったんだよね。

プロデューサーとしてレーベル運営にかかわる・ringsについて
原:じゃあなんでringsを始めたのかというと、ディスクユニオンのDIW productsというレーベル部門があって、いまringsもその一部なんだけど、菊田(有一)さんというDIWを立ち上げた方から、(ジャズ喫茶の)いーぐるで僕が出てたイベントのときに、「レーベルやりませんか」って声をかけられたのがきっかけだった。
で、「僕はもうレーベルはやらないです」ってはっきり断ったんだけど、あまりにも熱心に粘られて、「年に1、2タイトルでもいいので好きなものをぜひ出しませんか」といわれた。その熱意にほだされて引き受けることになったというわけ。それで、「ディスクユニオン側で担当を1人つけます」っていわれたから、以前から付き合いのあって気心が知れていた三河(真一朗、DJ Funnel)君を、部署が違うのに無理いって引っ張ってきてもらって、それで始めることになった。
最初に出したのが、LAでつながりのあったデイデラスとフロスティのアドヴェンチャー・タイムというユニットと、dublab.jpで企画した鈴木勲とDJケンセイのライヴを元にしたアルバムだった。それぞれ出すべきものだと思ったからだけど、それでとりあえずノルマも達成した気持ちだった。それを出したか、そのリリースを準備しているかのころに、レイ・ハラカミのリイシューの相談をご遺族から受けて、そこから急転直下、その翌年にはレイ・ハラカミの8タイトルを一気にリイシューしてた。だから、結果的には、レイ・ハラカミのリイシューがあったから続けることにもなったレーベルなんだよね。
針谷:それはいつごろのことですか?
原:2014年から15年にかけてのことだった。そもそもレイ・ハラカミとは、soupのころからスズキスキーと一緒にずっと付き合いがあって、二人のライヴを企画したこともあったし、スズキスキーの再発のライナーノーツを依頼したこともあった。というか、レイ・ハラカミとは散々酒ばっかり呑んでいたのが記憶の大半なんだけどね(笑)。ただ、そんな縁もあって、彼の作品を残していくということが、ringsの大きな仕事になった。それはいままでやってきたこととは少し違う責任を伴っていて、そこからレーベルをやっていくというスタンスも自ずと変わっていったと思う。
参考)
「REI HARAKAMIの時代」 日本のエレクトロニック・ミュージックの可能性を切り開き、40歳の若さで惜しまれつつ逝去したレイ・ハラカミの音楽とその時代を振り返る。
ringsをいまも続けている理由の一つは、レイ・ハラカミの作品を残していくという責任があるんだけど、もう一つは菊田さんが亡くなられたこともある。好きにやっていいとはいわれていたけど、レーベルが軌道に乗るようにかじ取りしていただいてたし、レイ・ハラカミのいろいろな交渉事で助けてもいただいた。そのことが常に頭の片隅にあるんだよね。あと、CDが売れなくなっても、ぎりぎり海外のライセンス・リリースをしているのは、自分が書き手でもあるから、やはりライナーノーツをきちんと付けて紹介をしたいという気持ちが強いからかな。配信だけでなく、フィジカルでリリースすることで広まるっていうのもまだ実感できることなんで。いや、でも本当に大変なんだけどね。
大きな予算は付けられないけど、こだま和文&Undefinedのように日本の作品を出せるときはうれしいよ。『2 Years / 2 Years In Silence』というアルバムは、UndefinedをやっているSaharaさんから相談されて、音源聴かせてもらって、これは必ず出さないといけないと思ったんだ。
あと、去年リリースした笹久保伸とファビアーノ・ド・ナシメントのギタリスト同士のアルバム(『Harmônicos』)は、一からringsで企画して作った。大磯のSaloという居心地のいいスタジオで録音を実現できたのは理想的だったよ。二人の作品を出したいというシンプルな理由だけでなんとか形にできたんだけど、予算を付けてちゃんと準備してリリースするのは難しいことも多くて、たぶんアーティスト側からすると、とりあえず自分たちで作ってしまおう、ってことになるのがいまは自然な流れだろうなと思う。昔soupでやってたのは奇蹟に近いというか、怖いもの知らずで、常識も欠いていたのもあるけど、CDやレコードがそれなりに売れていた状況もあったからだと思うね。
参考)
ファビアーノ・ド・ナシメント & 笹久保 伸『Harmônicos』はどう作られたのか? レコーディングを担当したスタジオSALOのエンジニア井口 寛と、アルバムのプロデューサー原 雅明の対話から紐解く
配信が一部の売れているアーティスト以外は売上に結びつかないことは散々いわれてるよね。だからいま逆にレコード作ったほうが手堅く売れるとか、CDでもライヴをよくやってるアーティストだと手売りで結構さばけるから、それでライヴやることと相乗効果で売上に結びついているんじゃないかな。CDを売るお店が少なくなっちゃったっていうのもある。レコードを売るお店は逆に増えてるように感じるけど。それも、昔の渋谷のような一点集中ではなくて、地方にいいお店が広がっている。あと、レコードをかける場所も増えているよね。
そこで実際に、レコードを買ったり聴いたりする人とコミュニケーションするのが大切にされていて、その関係性の中に音楽もあるということになってきてるのかな。でなければ、もうみんな配信で聴いて済ませちゃうよね。
針谷:以前、絵本作家のほしぶどう(DJぷりぷり・浅草橋洸彦)君から聞いたら、いまの若い人はなんでCDを買うかというと、ライナーノーツを読みたいから買うっていうことだったんですよ。
原:そうなんだ、それはうれしいことだな。

書籍『アンビエント/ジャズ』について〜90年代から一貫して求めてきた音について
針谷:マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノの接点というか、アンビエントなところでつながるという本を出されましたね。
原:もう読んでくれたの?
針谷:まだ全部細かくは読めていないんですが。
興味深かったのは、この本にはミュージシャンたちの貴重な言葉がたくさん引用されていて。加えて面白かったのは、例えばドミナントモーションなど楽曲の構造にも触れられているところでした。個人的な話ですが、私は、山下邦彦さんという、キース・ジャレットへのインタビューや坂本龍一の楽曲分析なんかをやって『坂本龍一全仕事』という分厚い本も出された方と、今年から電話をするようになって。コンピュータ・スープをやっていた当時は、楽曲の構造を知るのにとても面白いなと思って山下さんの本を読んでいたんですが、今回の原さんの本も、音楽をやってる方も興味深く読めると思いました。
またこの本では、アンビエントミュージックについて、ブライアン・イーノの、「非常に美しい、でも人を惹きつけすぎないような何か」という思想が書かれていて、アンビエントに近い音楽をやってきた身として妙に腹落ちしました。
そして、この本に書かれているアンビエントとジャズをつなぐ「音」が、原さんが90年代からレーベルsoup-disk以降、ずっと求めてきたサウンドと同じなのではないかと思ったんです。
原:「原さんって、同じことをずっと書いてますよね」っていわれたことがあったけど、人によってはそう捉えるられるのかもしれないね。ただ、自分は眼の前に現れてくる音をずっと追いかけているだけって感じなんだけど。
ジャズに関しては、特に前に出した『Jazz Thing ジャズという何か』(2018)が、21世紀の新しいジャズ、ロバート・グラスパーとか出てきた、その背景を80年代から追ってみた本だったけど、あれを書いて、結果的に自分がずっと聴いてきたジャズというものを再確認できた。フリー・ジャズもフリー・インプロヴィゼーションもストレート・アヘッドなジャズもいつしか対等に聴けるようになっていて、soupの初期のころに菊地雅晃君に勧められても毛嫌いしてたフュージョンもね(笑)。それは、2000年前後の変化が激しかった時代、あのあたりから急に聴けるようになったんだよね。なぜかはわからないけど、急に視野が広くなる感じがあった。そこからビバップ以前の古いジャズにも興味を持って、逆にいうと、ジャズに限らず即興演奏全般のあり方を一旦、客観的に見られるようになった。それまではどこか即興に偏重していたことがあったように思うんだ。それは一方でサンプリングやプログラミングでとんでもない音楽をやる人が出てきて、そこから刺激を受けたことも大きかった。

ともかく、2000年代にジャズをちゃんと聴き直そうとしていたときに、そういう新しいジャズが出てきて、ロイ・ハーグローヴがディアンジェロと一緒にやったネオ・ソウルやヒップホップともつながったタイミングでもあったんだ。それでさらにジャズをいろいろ意識的に聴き直すことにもなった。昔からジャズを聴いてたとはいえ、体系的に聴くことになったのは、そのころからだと思う。
それで得られたことはいろいろあって、それが『Jazz Thing』にも『アンビエント/ジャズ』にも反映されてるんだけど、ジャズを聴けば聴くほど、すごくヒエラルキーがはっきりする音楽だなって感じている。クラシックってそういうのがもっとはっきりしているよね。最上級の演奏家がいて、そこからのグラデーションが見える世界。ジャズもそういうものとして、演奏を楽しんでいるとも思うんだ。それはジャズという音楽そのものより、その解釈がそうさせているのかもしれないけど。
だから、ジャズを聴くのは、音楽を聴いてもたらされる解放感や音に身を委ねる感覚とはやや違う、「知的なゲーム」みたいなところがある。
本でもちょっと書いたけど、ブライアン・イーノのアンビエント、それは音楽に限らずアンビエント的な捉え方というものを含めてだけど、そういうのをジャズの対極に持ってくると、自分がジャズを聴いているときの閉塞感みたいなものが、イーノ的なパースペクティヴによって楽になるというか、ジャズを改めてフレッシュに聴けるなって感じがあった。それがこの本を書かせた個人的なモチベーションかな。
あと、マイルスに関する本は山ほど出てるよね。ディスクガイドもたくさんあるでしょ。でも自分がマイルスを聴いたとき、抑制的でアブストラクトな展開にアンビエントやドローンを感じた、その瞬間について説明している本はなかった。これは自分でちゃんと書かないとダメだと思ってまずは書き始めた。それが最初の具体的なきっかけだったかもしれないな。
針谷:ジャズやクラシックの中にあるヒエラルキーが気になったということですか?
原:ヒエラルキーは何にしろあるものだから、それ自体はいいし、番付表じゃないけど、それを楽しめればいいんだけど、そこにもう少し違う聴き方があってもいいと思うんだ。
針谷:解釈ですかね?
原:リスナー側の、リスニングの自由を担保したいってことかな。soupをやってたときに、僕と虹釜君がハマってたのが、菊地雅章と山本邦山の『銀界』というアルバムだった。ジャズと尺八の共演で、soupのコンピ『Silver World』もここから名前を採ったんだよ。あの当時は二束三文で売られてたレコードだったけど、演奏も録音もすべてがお気に入りだった。だから、DJクラッシュがサンプリングしてたのを発見したときは狂喜したね。それをネタに『ele-king』に原稿を書いたのを覚えてるんだけど、そういう感じ方の先にリスニングの自由ってあると思うんだ。『銀界』にある空気感や、それをサンプリングしたDJクラッシュのトラックにある空気感、そのつながりを発見して聴くこともリスナーの特権だと思ったんだよね。
針谷:そういうところからこの本になっているわけですね。
原:かなり端折った話だけど、そういうことも『アンビエント/ジャズ』の底流にはあったね。コンテンポラリー・ジャズを聴けば聴くほど、なんかこう、答え合わせをしているような感じを覚えてしまってた。なんでそう感じてしまうのか。それをジャズの中だけで考えてても堂々巡りだなと思ってもいた。そうしたら、昔からよく知るカルロス・ニーニョが、アンドレ3000やシャバカ・ハッチングスらとともに、アンビエント/ジャズ的な音を奏で始めた。なんでこの人たちはスピリチュアルなものとシリアスなものの間を自在に行き来できているのか、とそのときに感じた。そのあたりのちょっとややこしいけど大事な話は、『アンビエント/ジャズ』の「前書きの前書き」としてele-kingのサイトにも書いたけど。
それと同時に、ECMの音源をいろいろ聴き直していたタイミングでもあって、ECMがアメリカのジャズの本流と異なる価値観を確立していったプロセスというのも、要はいまと同じようなことを感じてた結果なんじゃないのかなって勝手に合点がいったんだよね。答え合わせをしないジャズというかね。そして、その先には、ニューヨークでずっと活動しながら日本的な何かを抱えていた菊地雅章が模索していたこともつながっていると思ったんだ。
この本のタイトル『アンビエント/ジャズ』に意図的に間にスラッシュを入れてるのは、ジャンルとしてアンビエント・ジャズっていうのを語りたくなかったからで、マイルスとイーノのことをそれぞれ語って、あくまでもその間を行き来しているってことを最後まで崩さないで書こうと思った。だからその意味でジャズを聴いてきた人にも、ちゃんと伝わるように書こうと、針谷君のいってた楽曲の構造的な説明も、最低限できる範囲ではしたつもりだけどね。
参考)
音楽を高めるためには何が必要か。LAシーンの導師、カルロス・ニーニョが語る
『アンビエント/ジャズ──マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜』刊行に寄せて──著者・原雅明による「前書きの前書き」
針谷:この本に書いてあったことで、BGMとアンビエントの違いは、「不安定性」みたいなものがアンビエントにはあるっていう、ところに近いことですかね。
「綺麗な音楽」「テクニックの上手さ」というところとは外れた。
原:一見、綺麗な音楽なんだけどよく聴くとちょっと変な音が入ってるとか。そのバランスに秀でてると思うんだよね。ただふわっとしてる音に感じても、注意して、解像度を上げて聴くとこんな音が入っているんだと気づく。でも、注意して聴かなくてもいいから、気がつかなくてもいい。
それはジャズでもそうで。僕が面白いと思うジャズは、一見かっちりしてるんだけどちょっとしたズレや破綻、逸脱を許容している。それも気がつかなくてもいい。気がつかないことが間違っているわけでもない。要はその塩梅の妙なのかな。
針谷:そうですね。わかります。
基本的に昔から、原さんの求めている音は一貫してますね。この本を書くのにどれくらいかかったんですか?
原:実際の執筆期間は8ヶ月か9ヶ月くらいかな。でも、その前から考えていたことの積み重ねがあったから、いきなりゼロから書き始めたわけでもない。そもそも、編集者の小林(拓音)さんから話をいただいたのは3年ぐらい前だったと思う。まずは自分からアイデアを出しますといったんだけど、一向に出さないでいた。ただ、たまに小林さんとやり取りしていたときに、なんで僕に頼んだかという理由を明かされて、それで俄然やる気になったんだよね。というのは、小林さんがロレイン・ジェイムスのライヴに行ったときに、会場でずっと熱心に『Jazz Thing』読んでた人がいて、これは何かあるだろうという編集者の直感が働いたらしい。その理由が気に入ってしまって(笑)、もう一回自分が昔書いた原稿を読み直してたら、『TOKION』にマイルスとイーノと菊地雅章について書いたコラム的な原稿が目に留まった。5年くらい前に書いたもので、書いたときにも手応えを感じていたんだど、これを膨らませる形でどうかなって見えてきて、そこから書き始めた。マイルスのところとイーノのところは、ほぼ書き下ろし。ECMのところは自分で書いたライナーノーツも再構成したけど、書き下ろしが多い。あと最後の日本の音楽のところも大半は書き下ろしだったね。
針谷:本の後半に日本のミュージシャンが出てきますよね。
原:最後の章で取り上げた、菊地雅章さん、尾島由郎さん、清水靖晃さん、高田みどりさんについては、それそれ実際に会ってインタビューをしたことから書くことができたんだけど、その出会いが、マイルスとイーノから始まった本が行き着く先を自ずと示してくれたし、この章がなかったら、この本は成り立たなかったと思う。そして、日本の音楽から、この先のストーリーをまた紡いでいけるんじゃないかとも思っている。あと、菊地さんの「六大」というエレクトロニック・ミュージックのシリーズを、ringsで来年リイシューできることになった。本当は本の刊行と同じタイミングで出すつもりで本でも詳しく触れたんだけど、マスターを探し出すのにとても手間取ってしまった。リマスタリングをテイラー・デュプリーに依頼してさらにすばらしい音になったので、これも『アンビエント/ジャズ』の続きとしてぜひ聴いてもらいたいんだよね。
針谷:今回の本は、前回の『Jazz Thing』よりも、失礼かもしれませんが、最初から最後まで一貫したものを感じました。
原:『Jazz Thing』は過去の原稿を集めて、最初の章だけ書き下ろしを加えたものだったけど、今回は全体の主旨が見えてから書いているから、そういう意味では筋が通ってるんじゃないのかな。過去に書いたものもテーマに沿ったものだけを入れてるから。
針谷:イーノとマイルス?!という驚きがまずあって、最初から引き込まれて読み進められましたね。
とても面白く読ませていただきました。
原:ありがとうございます。

新しい音楽の可能性について・リスニング
針谷:この前、私がたまたま行った渋谷のBAROOMでのイベントでもDJをやっていましたね。
原:あのときは、イベントのDJじゃなくて、通常営業しているバーのミュージック・セレクターだね。DJよりも、レコードをかけるセレクターっていわれるほうが自分はしっくりくる。昔からDJ的なことはやってたけど、DJなんて名乗るのはおこがましいとずっと思っていた。盛り上げるニーズに合わせるなんてできないし、常に「そうじゃなくてもいい」DJみたいな隙間の立ち位置でやっていた。気持ちよくつながれていくグルーヴも好きだし、Low End Theoryで強烈な低音を体感することも好きだったんだけど、一方でBPMに束縛されないでかけたいというのがあった。といっても、完全なフリージャズとかノンビートものをかけるのも躊躇してた。でも、いまは違ってきたと思う。リスニングそのものへの関心というのが高いように感じるんだよね。
この間、オーディオテクニカのAnalog Marketという築地本願寺でのイベントで、日本のフリージャズのレコードを聴くというリスニングの場を仕切ったんだけど、無料のイベントだし、お客さんは途中で帰ってしまうかなと内心思いつつ、レコードをかけていた。でも、1時間ほど、皆さんじっと聴いてくれていた。すばらしい音響システムと特別な場所だったというのもあるけど、音に浸って聴くという体験が受け入れられているのを実感できたんだよね。しかも1人で聴くのではない。何人かの人と一緒に聴く体験っていうのは、新鮮な感じがあるのかもしれないね。
針谷:全生新舎がやっている野口晴哉記念音楽室でもDJをやっていましたね。
原:あれもDJじゃなくてレコード・セレクター。岡田拓郎さんを招いて『アンビエント/ジャズ』の刊行記念もやったんだけど、あの音楽室でレコードを聴く体験は本当に特別だった。だいたい1人で2時間くらいレコードをかけて、トータル、4、5時間はあの音楽室で来た人と過ごすんだけど、全然長く感じない。本当に不思議でほかでは得難い時間感覚と聴取体験なんだよね。
針谷:そこでは、お酒を飲みながら聴けるんですか? ワンドリンク制と書かれていたので。
原:もちろん、お酒も飲めるし、ジャズ喫茶みたいに私語厳禁でじっと聴いてなきゃいけないってわけでもない。音に浸ってもいいし、庭に出たり、ちょっと離れたところで漏れ聞こえる音を楽しむようなこともできる。集中して聴くことと、アンビエントみたいに音が流れてるのを聞くことの狭間にある状態が、あの音楽室では作り出されていて、その在り方もとても興味深いんだよね。詳しいことは、全生新舎主宰の野口晋哉さんにインタビューした記事があるから、それもぜひ読んでみてもらえたらと思う。
野口晴哉記念音楽室には『アンビエント/ジャズ』を書き上げてから出会ったんだけど、それ以前から「リスニング」について得られたことが本にはフィードバックされていたから、そのことを再確認するような体験でもあった。というか、『アンビエント/ジャズ』とつながっている世界が、突然現れたような感じだった。でも、それだけじゃなくて、この数年DJとして参加しているEACH STORYという野外のイベントでのリスニング体験から得られたことも多々あったし、dublab.jpが尾島由郎さんと進めているKankyo Dotという環境音楽のインスタレーション・プロジェクトや、「Ambience of ECM」というECMのリスニング・エキシビションを企画したことからのフィードバックも、本にはあった。それらに共通するのは、リスニングというのがとても能動的で創造的な行為で、リスナーという存在を鼓舞するものだと気付かせるということ。そういったさまざまな実体験も『アンビエント/ジャズ』の背景にはあるんだよね。
針谷:10年ほど前、健康を考える中で、たまたま野口晴哉さんの常識を覆す著作の数々に出会いましたが、その子孫の方が音に向かわれているのは、とても興味があります。
ありがとうございました。もう一度、じっくり読んでみますね。
参考)
野口晴哉記念音楽室が再生する新たなリスニングについて。全生新舎主宰、野口晋哉氏に訊く
ジム・オルークが石橋英子と語る、音楽を取り巻く「少し変」なこと。音楽体験を拡張する環境と文脈の話
原雅明×尾島由郎が語る「ジャズ」と「環境音楽」の交差点。『アンビエント/ジャズ』刊行記念トーク・レポート
原雅明プロフィール
文筆家、選曲家、プロデューサー。各種媒体への寄稿やライナーノーツの執筆の傍ら、レーベルringsでレイ・ハラカミの再発などのリリースに携わり、ロサンゼルスのネットラジオ局dublabの日本ブランチの設立に関わる。リスニングや環境音楽に関連する企画、ホテルの選曲を手掛け、都市や街、自然と音楽とのマッチングにも関心を寄せる。早稲田大学非常勤講師。著書に『アンビエント/ジャズ――マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜』(Pヴァイン)、『Jazz Thing ジャズという何か』(DU BOOKS)など。











